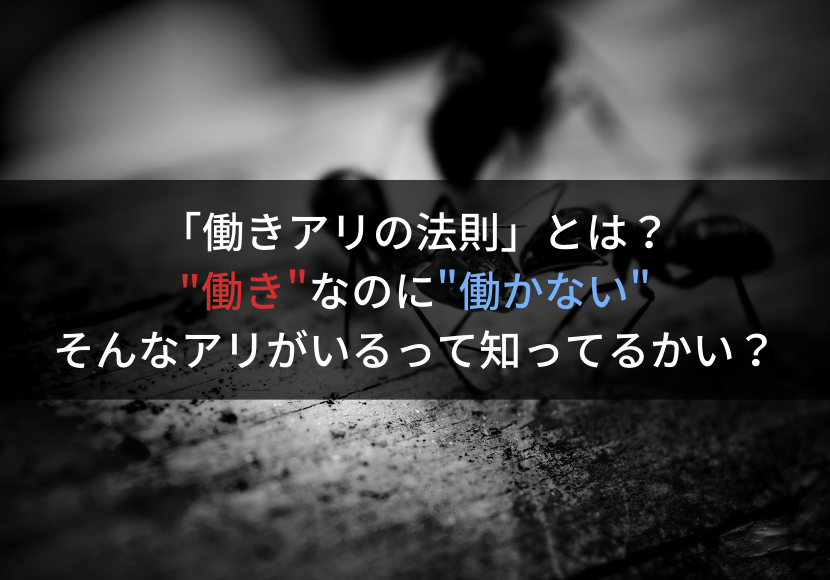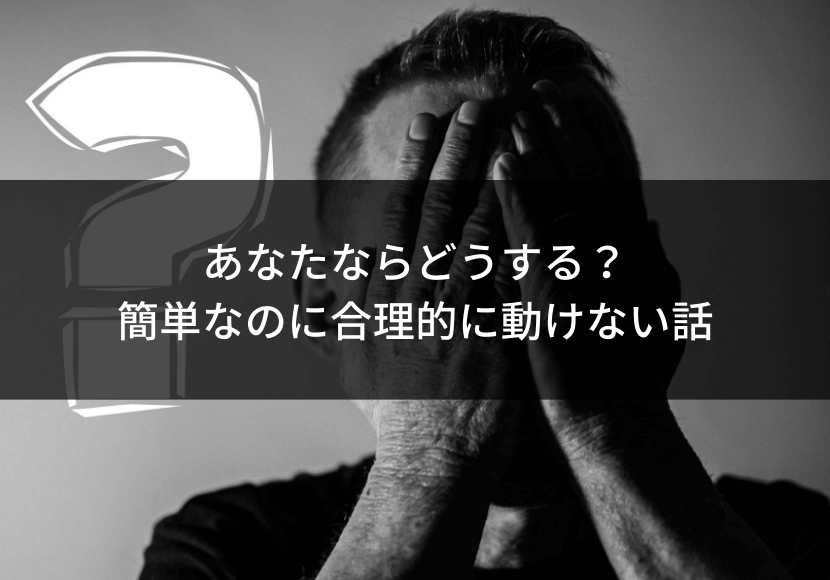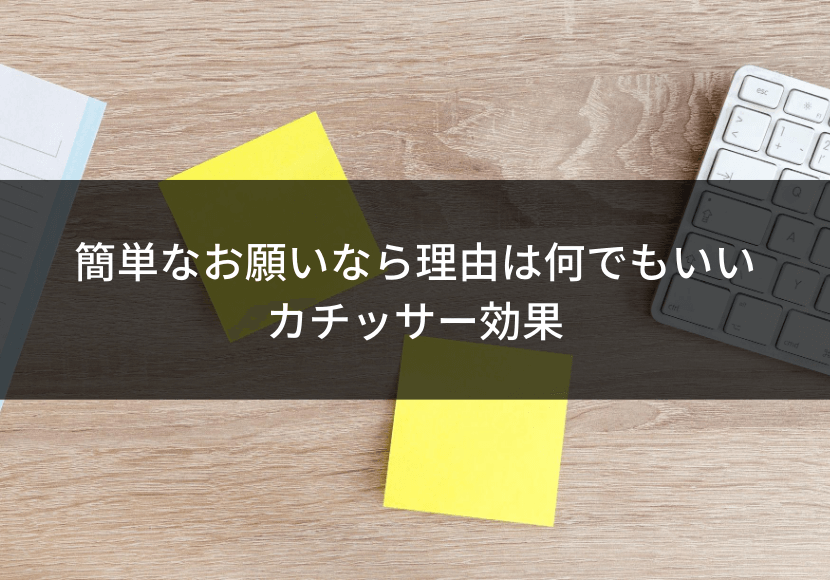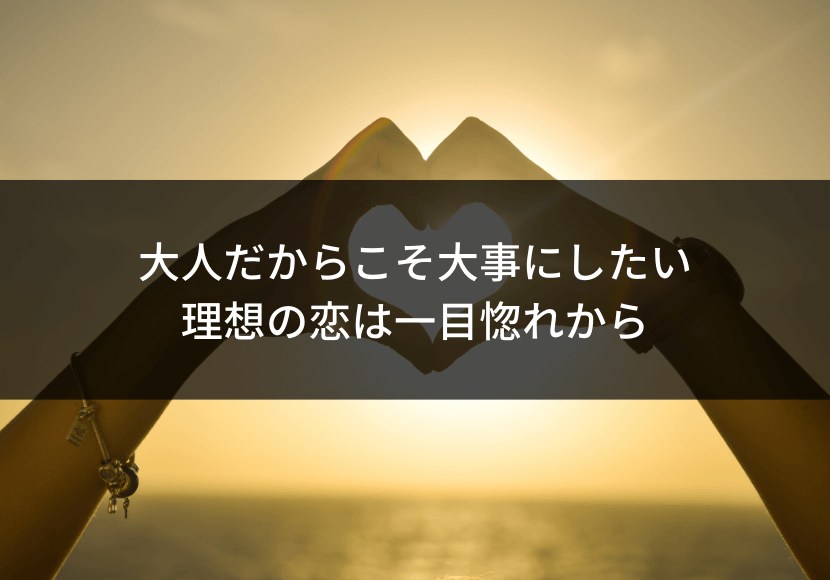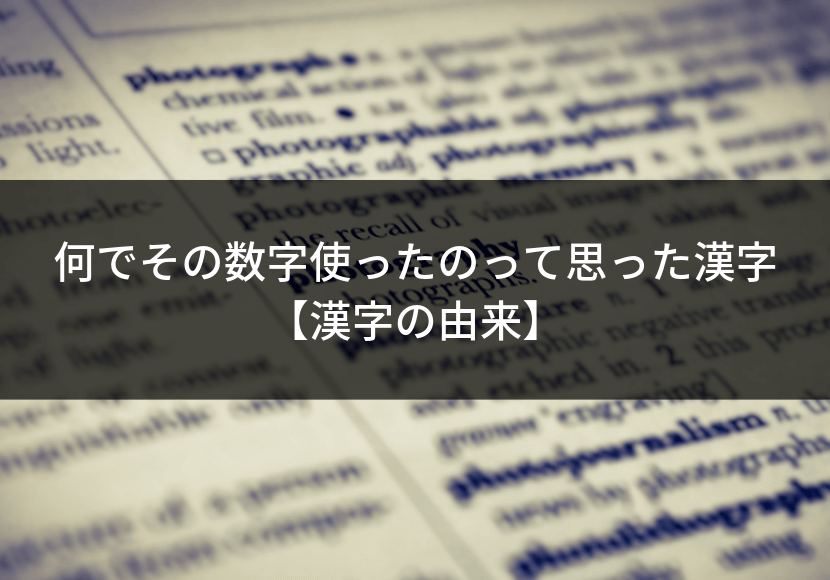
昔から在るであろう言葉で「どうしてそうなった?」って思う漢字がいくつかあった。
共通点は数字を使った言葉だと言うことなのだけど、今回はそれらの言葉をいくつか調べたので共有したい。
人一倍
【意味】
人よりも倍(~する)。
【疑問】
「一倍なの?一緒じゃない?」って思わない?
全然追い抜く努力してねーじゃんアイツって思われちゃうよ。
【理由】
江戸時代に使っていた”倍”にはそもそも2倍って意味があったらしい。
今でいう3倍、4倍とか3倍以上を表現する時は層倍って言葉を使って、3増倍とか4増倍とか言ってたみたい。
なので当時の”倍”が意味するのは2倍の事だった。
それが時代の経過で統一されて、今みたいに3倍4倍って言うような流れになったんだと。
四苦八苦
【意味】
非常な苦しみ。
【疑問】
4回とか8回とか苦しんで、ずいぶん大変そうですね!
漢字だけで大変なのは察するけど、4と8じゃ倍ほど違うけど…話盛ってます?
ってなる程にどこから出た数字かわからない。
【理由】
仏教の生・老・病・死の四苦に以下の4つと、さらに以下の4苦を加えたもの。
愛別離苦:家族とか大事な人と別れる苦痛
怨憎会苦:嫌いな人と会わなければならない苦痛
求不得苦:欲しいものが手に入らない苦痛
五陰盛苦:体と心を構成する5つの要素から生まれる苦痛。
五陰は色・受・想・行・識を指すらしいけど、それぞれの意味は見ても覚えられないくらいハッキリしないので割愛。
八苦の内、一苦でも該当したら四苦八苦って使っていいのだろうか?
4つくらいの苦しみが無いと、本気で四苦八苦してる人に失礼とか無い?
わかんないから、何か言葉が重いので軽々しく使うの控えよう。
御三家
【意味】
代表的な三つの家柄を敬って言う言葉。
【疑問】
お笑い御三家とか、様々なジャンルのビッグスリーを指すのに御三家って使うけど、何で家なの?
どこのお宅の方ですかっての。
【理由】
江戸時代の尾張・紀伊・水戸の徳川三家の総称する言葉。
一つの括りの中で有力な3つって事で、徳川御三家に由来した使い方をしてるっぽい。
今更だけど、人を指すなら御三方とかじゃダメだったのかねーって思っちゃう。
十八番
【意味】
得意なもの。
“おはこ”とも読む。
【疑問】
意味は分かるけど、十八の出所を知りたい。
「十八番出すぞ」って言われると「いや、一番出せよ」ってクソしょうもない事言いたくなる。
【理由】
色々と諸説があるらしいけど、歌舞伎から出来た言葉らしい。
歌舞伎の台本「歌舞伎十八番」で得意な演目を十八演目に用意したことから使われだした言葉。
おはこの読みも「歌舞伎十八番の台本を箱に入れたから」って見たこともあるので、そのまんま。
もし台本を箪笥で保管してたら十八番と書いて”おたんす”だったわけだ。
一か八
【意味】
運任せ。出たとこ勝負。
【疑問】
なぜ8なのだ。
せめてキリ良く9とかさ、あったでしょ。
【理由】
これまた諸説があるそうだけど、賭博用語らしい。
丁半賭博で「1が出るかハズレが出るか」の意味で「1か罰か」の言葉があり、少し変化して「一か八か」になったそうな。
“バチ”って打つと”罰”に変換される。
マジかよ。
七転び八起
【意味】
何度失敗しても、何度も奮起する事。
【疑問】
7回転んで8回起きる。
起きる回数1回多いですよ。
【理由】
どうやら数字に意味がないのだとか。
ただ沢山の挫折を表すのに大きめの数字を使っている様子。
7とか8は縁起良いから使ってるってのも見た事ある。
ちなみに1回多い起き上がりは、何かを思い立った時を1回目と考えるかららしい。
まとめ
今回の言葉を調べると、同じような疑問を持ってる結構人がいて、「みんな気になる所一緒だな」って思ったら笑えた。